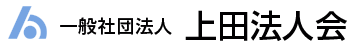国外居住親族に係る扶養控除の取り扱い
経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答
税理士 互 井 敏 勝
国外に居住している親族(国外居住親族)を扶養控除の対象としている従業員から、扶養控除の制度が変わっているようだが問題ないか相談を受けたのですが、何か改正されましたか? この従業員は、フィリピンに居住している母親(65 歳)に、毎月生活費として3万円送金しています。
令和5 年1 月以後に支払われる給与等について、国外居住親族に係る扶養控除の対象となる親族から、年齢30 歳以上70 歳未満の者のうち、①留学により非居住者となった者、②障害者、③給与等の受給者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者のいずれにも該当しない者が除外されました。したがって、ご質問の場合、従業員の母親が留学により非居住者になった者か障害者でなければ、年間で38 万円以上の生活費又は教育費に充てるための送金が必要になるので、毎月3 万円の送金では年間36 万円となり、現状では扶養控除の適用を受けることはできません。
そうなのですね。扶養控除の適用を受けるためには送金額を増やす必要がありますね。なぜこのような改正が行われたのですか?
これは、年齢が30 歳から69 歳までである非居住者は所得の稼得能力があると考えられることから基本的には扶養控除の対象外としつつ、所得の稼得能力があると考えにくい学生や障害者は引き続き扶養控除の対象とできることとし、さらに、年間で受け取った送金額が38 万円以上である者についても、真に所得が低い可能性を否定できないことなどから、扶養控除の対象となることとされました。
この従業員の母親は留学により非居住者となった者や障害者には該当しないようですが、扶養控除の適用を受けるための手続きを教えてください。
給与等の支払者に給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に、国外居住親族が給与等の受給者の親族であることを証する書類を提出等する必要があります。さらに、年末調整の際には、その年中に支払った金額を記載した扶養控除等申告書を提出等するとともに、その年における支払金額の合計額が38 万円以上であることを明らかにする書類を提出等する必要があります。
扶養控除の対象に該当するか否かの判定は、いつの時点でどのように行うのでしょうか。
扶養控除の対象に該当するか否かは、扶養控除等申告書を提出する日の現況において見積もったその年中の支払金額で判定します。
見積金額で判定するのですか。実際の支払金額が38 万円未満となった場合はどうなりますか?
年末調整において、結果として、その年中の支払金額が38 万円未満となった場合には、その国外居住親族について扶養控除の適用を受けることはできないことになります。
なるほど。年末調整の際には、国外居住親族へのその年の送金の合計額が38 万円以上であることを確認し忘れないよう注意が必要ですね。
【筆者紹介】
スマホ、PC…うつむく姿勢が危ない
産業カウンセラー 柏 木 勇 一
◆テレワーク、ひとり自宅でのPC 作業で首痛に
建築会社の設計士として働く30 代のM さんは、大卒後入社して一級建築士の資格も取得、中堅社員として会社の成長にも貢献してきた。コロナ禍でテレワークの日々。現場作業員や営業職は出勤していたが、PC による設計業務は在宅でも十分可能だった。むしろ、作業に集中できる利点があった。自宅から駅までの徒歩や電車での往復時間がない分、作業できる時間も多くなった。そんな日々が続いて1 年半。首の痛み、頭痛、手のしびれを感じるようになり、近くの整形外科医院へ。頚椎(けいつい)椎間板ヘルニアの疑いと、手術が必要になる可能性があることも指摘された。驚いたM さんは会社の健康管理室に相談、産業医(内科医)から理学療法士を紹介された。戸惑いもあったが、結果的にはいい展開になった。
◆それは現代病のひとつ、理学療法士の原因説明に納得
理学療法士はまず、最近特に首から肩にかけての痛みを示す「頸部(けいぶ)痛」の発生が増加していること、その原因の多くは、PC 作業とスマホの普及と説明。M さんは自宅で長時間うつむく姿勢で作業していることから、常に首に負担がかかっていたことを指摘した。椎間板がつぶれやすくなっていること、椎間板にある髄核という物質が飛び出して痛みやしびれにつながっていることなどから、「一種の現代病」と丁寧に語り、M さんも納得した。さらに療法士は、成人の頭の重さは体重の約10% で6㎏前後。首周りの筋肉はこの重さを支えるために活動し、15 度うつむくだけで頭を支えるために生じる負担は12㎏前後まで増加すること、何も手を打たないと筋肉は疲労し、痛みや肩こり、しびれやめまいなどの不調が日常化する恐れがあることも語ってくれた。
◆背筋を伸ばし画面との距離も意識、やっぱり休憩が大切
頸部痛を防ぐにはどうすればいいか。M さんの場合は、PC の使用時間をできるだけ短くすること。うつむく姿勢を改め、目線の高さで作業するという、とりあえずの結論が出た。M さんは療法士の説明を受けて、出社の場合は当然歩くし、職場では同僚との会話でPC から離れ、休憩や昼食時間は会話も欠かさなかったこと、つまり一日中デスクワークの在宅ではそういう余裕の時間がなかったことに気づいた。そこから、在宅でも部屋から離れて散歩や太陽の光を浴びることを心がけ、作業中は猫背にならないよう足をフロアにつけ、背筋を伸ばして画面との距離も意識するようになった。
スマホを手放せない時代になり、頸部痛は「スマホ首」とも呼ばれて、現代病のひとつとして問題視されている。実は、PC やスマホだけではなく、料理をする際もうつむいてしまう人が多く、これも要注意。手術が必要になる病気になる前に、PC に向かう普段の姿勢はどうなっているか、コロナ禍で働き方が変わった現代人にはぜひ知ってほしい。スマホでのゲームやアプリ検索も日常化している時代。スマホと目線の高さは大丈夫ですか。